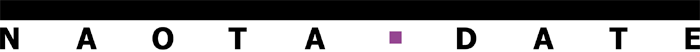|
|
取材後記 2023 |
|
 |
労働集約型の仕事について 12月某日 晴れ |
例年のように、年末年始は仕事をして過ごす。
今年は福祉施設に関する原稿を書きながら新年を迎える。本来は年末までに脱稿する予定だったが、数日遅れることをあらかじめお詫びする。来年の年末はちゃんとやります。
さて、福祉の原稿を書くにあたって周辺事情を調べていくと、なかなか厳しい業界であることが分かる。主な課題は人である。
福祉施設は労働集約型である。つまり人が動いてナンボの仕事で、人がいないと成り立たない。しかも、給料が安かったりハードワークだったりといった処遇の面で人が集まらない。従業員の定着率も低い。
人が集まらない原因としては、日常生活で福祉との接点を持つ機会が少なく、身近に感じられないのも一因ではないか。身内の高齢者と一緒に暮らしていれば介護サービスなどが身近に感じるが、核家族だと実感が得られない。日本は6割が核家族である。福祉のお世話になる機会がなければ福祉の仕事に興味を持つ機会も減る。どんな仕事かもよく分からない。中年の私ですら福祉についてよく知らないのだから、勤め先を選ぶ若い層はもっと縁遠く感じるだろう。
学生に人気がある就職先ランキングを見ると、近年はコンサルが上位の常連である。気持ちは分かる。キラキラして見えるし収入も良い。
ただ、福祉もコンサルも労働集約型の仕事であるという点では同じである。私はコンサルファームとの付き合いがいくつかあるので、彼らがどれくらいハードワーカーか知っている。キラキラした部分もあるが、実際の業務は泥臭い。勉強量も多い。一般企業と比べてコンサルファームの離職率が高いのは、キャリアアップのために退職する人がいる一方で、ハードワークについていけない人も一定数いるからである。つまりこれも人の課題で、採用と定着の話に戻る。
人口減少が確実な時代の中で、労働集約型の企業が人の採用と定着の課題を解決する方法は2つしかない。1つは企業や業界の価値向上である。学生の人気がコンサルファームに集まるように、業界や企業が魅力的であれば全体として人材の獲得競争に勝てる。それが難しければ、もう1つの方法はロボットである。デジタル化やAI活用も含めて、人が担っている仕事を機械に任せる。これで人手不足は穴埋めできる。いずれはロボットが介護や介助をして、経営のアドバイスもするようになるのかもしれない。物書き商売も労働集約型である。何年かすれば、ChatGPTに原稿を任せて、穏やかな年末年始を過ごせるようになるかもしれない。 |
ググることについて 11月某日 晴れ |
ググる、という言葉がある。
Googleで調べるという意味で、「ぐぐる」と打てば「ググる」と変換されるくらい一般的な言葉になっている。先日聞いた話によると、今どきはググる人が減っているらしい。ググらずにどうするかというと、気になる言葉があった時に、YouTube、X(旧Twitter)、インスタグラムの検索を使う。あの虫メガネアイコン、そういう使い方するものだったのか。
ググって出てくる情報はその言葉に関する概要や説明にとどまるが、SNSの検索はリアルタイム性を加味した情報が得られる。YouTubeで検索すると動画で深く知ることができる。文字情報と比べると、画像の情報量は7倍、動画の情報量は5000倍だという。調べ物ひとつでもネットリテラシーの高さで差がつく時代だ。
たまに電車に乗ると、ほぼ全ての人がスマホを見ていることに気づく。ゲームをしている人、Youtubeのような動画を見ている人、Xやインスタを見ている人など、やることは人それぞれである。
その中には暇つぶしにSNSやYoutubeを見ているように見えて、勉強したり調べ物をしたりして知識を習得している人もいるのかもしれない。そう考えれば、勉強は場所と時間を問わない。学習においてもネットリテラシーの高さで差がつく。車窓をぼんやりと見ている場合ではない。
情報を得るという点では、現地現物を重視する考えは今も根強い。たしかに、味や匂いや温度など、五感を通すことでしか得られない情報もある。
ただ、視覚と聴覚はバーチャルでもかなりリアルに体感でき、バーチャルとリアルという境界線はすでに極めて薄い。変な表現だが、バーチャルの世界におけるリアル性がかなり高くなり、リアルの世界におけるバーチャル性も高くなっている。例えば、ニコニコしている人がじつは腹を立てていることがある。これはリアルの世界にあるバーチャル性である。そしてネットで苛立ちを吐露する。これはバーチャルの世界のリアル性である。つまりバーチャルもリアルもどちらも現実の世界であり、私たちは2つの世界を行ったり来たりしながら生きている。
リアル性のあるバーチャルの世界にはググっても入れない。ググることで見えるのは概要であって、要するに建前だからである。そう考えると、若い人たちがググらなくなった理由も分かる。情報の価値という点で、現地現物では掴みきれない情報が匿名性に守られたバーチャルの世界で得られるからである。 |
起業について 11月某日 晴れ |
タピオカ屋はどこへ行ったのか。
縁があって、そのようなテーマの本の出版を手伝っている。
恥ずかしながら、私はタピオカミルクティを飲んだことがない。子供らは好きだし、出先で買わされたり、なんなら買ってこいとパシリにされたりすることもあるが、私自身は甘党ではないし、あの独特の見た目に多少の抵抗感もあって、一度も飲んだことはなく、一生飲まなくてもいいかなと思っている。
ブームは盛り上がる熱量が大きいほど廃れるのが早くなる。商売上手はその変化に敏感で、タピオカ屋を出して短期間で稼ぎ、ブームが去る前に違う事業に乗り換える。その姿勢に事業化と事業家としてのヒントを探ろうというのが「タピオカ屋はどこへ行ったのか」である。世界各国と比べて起業に奥手と言われることが多い日本の市場において意義のある問題提起だと思う。
データを見ると、日本の開業率は5%程度であるらしい。米国など他の先進国の半分くらいの数値だ。また、起業を望ましい職業選択と考える人の割合は、日本は25%ほどであり、中国は80%、米国は68%である。日本においては小さな事業を起こすことよりも大きな企業の一員となることの方が高く評価されていることが、これら数値を見るとよく分かる。
起業も企業勤めも、どちらも一長一短であるから良し悪しは分からない。ただ、私は小さな商売をしている身であるから(企業勤めをしたことがない身でもあるので)、チャンスがあるなら起業に挑戦してほしいと思う。リスクはあるがリターンも大きい。ちなみに物書き商売のリターンは、経済的なリターンというよりは時間的自由や精神的安定である。
ところで日本人の平均寿命は世界一である。平均寿命そのものも伸び続けている。そう考えると、やってみたいことがあるなら、という前提だが、起業はなおさらおすすめである。成功させる時間的余裕があり、失敗して出直す時間も相対的にあるからである。
起業は若いうちがよく、失敗による絵遅れを取り返せるという点でも若い人の特権のように語られがちだが、長寿であるなら高齢になってからの起業も十分にあり得る。2000万円貯めて慎ましい老後を過ごすのも手だが、引退から20年もの時間を消化試合のように過ごすのであれば、2000万円を元手に起業してみるのも手なのではないか。高齢者は年金と医療費の食い潰しによって叩かれがちだが、起業すればもしかしたら社会の役に立って感謝されるかもしれない。そういう意識を高めていくこと、また高齢者の起業をブームにするくらいの風土を醸成していくことも世界一の長寿国だからできることの1つだろう。 |
コンピュータのすごさについて 10月某日 晴れ |
コンピュータは中国語で電脳という。
その字の通りで、人の脳の機能を電子化したものである。成り立ちを見ると、コンピュータは計算機が原型であるらしいから人の脳とは異なる。人は計算ができるようになる前にさまざまなことを記憶する機能を備える。母親の顔を覚えたり言葉を覚えたりする。コンピュータで言えば磁気ディスクのようなもので、順番としては演算が先で磁気ディスクが後だった気がする。その正確な答えもコンピュータに聞けば分かる。
世界中にコンピュータが普及し、社会で活動している脳の数が増えた。スマホも含めれば10倍、あるいはそれ以上に増えたのではないか。
おかげで人は計算や記憶をしなくても生活できるようになった。目的地までの距離や所要時間を計算してくれるし、街中の防犯カメラが周囲の変化を全て記憶する。しかも、その能力が極めて高い。計算を例にすると、スマホは1秒間に10億回くらいの計算ができるという。スーパーコンピュータの富岳に至っては44京回の計算ができるらしい。これだけ圧倒的な差があるなら「餅は餅屋」で人は計算をしないほうが効率的である。
シンギュラリティという言葉がある。その意味はAIが人の知能を超えることだ。その世界においては、AIが新しいAIを作り出す。「Singularity is Near」を書いたレイ・カーツワイルは、その時期は2045年だといっている。カーツワイルがいう「収穫加速の法則」を踏まえれば、その時期はもっと早いかもしれない。
ふと「もう追い抜かれているのではないか」と思うこともある。例えば、人の脳は1度に1つのことしか処理できない。これはスマホに似ている。X(ツイッター)のポストを見ながら株のソフトを操作することはできない。表面的なオペレーションはシングルタスクだ。
しかし、パソコンならマルチタスクだ。株価チャートの動きを見ながらXのタイムラインを更新できる。それらを見ながら原稿を書いたり、ラジオや音楽を聞いたりすることもできる。
もっとも、人のほうはシングルタスクであり、感情にも左右されるため(ここもコンピュータとの違いだ)、持ち株が下がっているのを見ると原稿を書く意欲が失せる。そういう揺らぎも含めて、人はすでにコンピュータに抜かれたのではないかと思う。人の脳を模して生まれたはずのコンピュータは、すでにオリジナルを超えている。シンギュラリティ世界への漠然とした恐怖は、オリジナルの価値が失われることへの警戒心と不快感なのだと思っている。 |
市場の変化と事業の継続性について 10月某日 晴れ |
現状、半年先まで単行本の執筆予定が埋まっている。
「もっとも予約が取れないライター」を目指している私にとって、これは良い傾向である。そのおかげで売り上げが伸びていることも大事だが、予約は事業の継続性を高める。おかげで物書き商売がだいぶサステナブルになった。
予約をいただける要因の2つある。1つは、雑誌の仕事がほぼないからだと思う。これは数字で見ると分かりやすい。2014年からの約10年で、書籍の市場規模は1割ほど縮小し、雑誌は半分近くになった。私は雑誌をやっていないので、その影響がない。これは予約が増える要因ではないが、減らない要因にはなっている。
もう1つは事業モデルである。作家先生の収益はB to Cによる印税収入が主だが、私はB to B to Cである。つまり読者層であるCとの間に私の直接の取引相手である出版社や代理店といったBが入り、私の存在がCの眼に触れることはない。契約内容についても文字数やページ数で計算する買取りがほとんどであり、したがって印税でがっぽり儲かる可能性はほとんどないが、その代わり、市場の本離れや雑誌離れが進んでも、それほど影響を受けない。
フリーランスは不安定の代名詞みたいなものだから、サステナブルに稼げる市場と事業モデルを見つけなければならない。言い換えれば、文章が上手いだけでは商売にはならない。書くことが好きという情熱だけでも長続きしない。
ここは世の中に誤解されやすいところだ。物書き商売は、必要最低限の素養として物書きの芸術性と矜持が求められるが、同時に、どこでどうやって稼ぐか、長く続けるにはどうするかといった科学的でマーケットドリブンな視点も必要である。
そういう視点を持って私が今の事業モデルを作ってきたかというと、そんなわけない。当初は雑誌向けの単発の原稿などを書いていた。ネット向けの小さな記事も書いた。その後、印税が発生する書籍の仕事をするようになり、社内報などインナーツールの仕事もするようになった。
節操なくいろいろと手を出していると、そのうちにオーダーの濃淡が出てくる。濃淡は、雑誌の仕事が少なくなったり、社内報の仕事が増えたりという変化である。それに流されるように仕事の内容を調節してきた結果が今である。
雑誌がやりたいとか作家になりたいとか、そういう傲慢なことは考えたことがない。評価するのはお客さんであり、評価されれば次の仕事が来る。そういう市場ありき姿勢で自分に求められている役割を理解して、その分野の勉強をしてきた。その結果、気づけば仕事が増えて、サステナブルになってきたというのが実態である。 |
物価高について 10月某日 晴れ |
私は節約派ではない。日々の買い物もほとんど値段を気にしていない。
その程度に物価に鈍感な私でも、食料品や日用品などを買ってお金を払うときに「なんか高えな」と感じる機会が増えた。先日は「たまごって300円もしたっけ」と感じた。感覚的には、今まで5000円で済んでいた数日分の食費が8000円くらいになっている気がしている。
気になったので調べてみたら、直近のCPI(消費者物価指数)は前年同月比で2%以上も高くなっている。すでに2022年は年間で10%以上物価が上がった。5000円から8000円に跳ね上がるほどではないが、じわじわと高くなっている。気づけば日銀の物価上昇目標である2%を超えている。
外部環境を見れば、エネルギーコストも高いし、猛暑の影響で野菜が一部の不作である。たまごの価格は鳥インフルエンザが影響している。国産が高いなら輸入品でしのぎたくなるが、今は1ドル150円前後の円安である。よく考えてみれば値上がりの要素ばかりである。
教科書的には、インフレは必ずしも悪ではない。価格が上がって企業が儲かれば、社員の給料が増える。社員は一方では生活者であり消費者でもあるから、収入が増えて購入力が高まり景気拡大につながる。学問上の良いインフレは存在する。
果たして今のインフレはどうだろうか。給料が増えた会社もありそうだが、周りを見る限りでは景気が良くなったような雰囲気はない。手元の帳簿を見ても、ありがたいことに収入は前年を上回るペースだが、手元に残るはずのお金は物価高に持っていかれている。
いよいよデフレからインフレの時代に変わるのだとしたら、モノの買い手として物価高を対策すると同時に、売り手の意識も変えなければいけない。
デフレ時の戦略は「良いものを安く作る」ことだった。日本はこの戦略が得意だ。日本式の経営はお客さんに弱い。値下げを「勉強させてもらう」と言ったり、「お客さまが神様」と言ったりもする。
しかし、それではインフレ時代の成長は実現できない。より良いものを作り、高く売る戦略が必要になる。それができれば、新たな付加価値が生まれて日本全体が成長する。振り返ってみれば、30年にわたるデフレの中で、日本はその努力を怠ってきた。今の物価高が衰退途上国の状態から成長国に変わるための成長痛であるとするならば、未来の日本の成長を生み出すために、1000円カットの店は1200円に値上げし、消費者は300円の卵を買う。そういうタイミングなのかもしれない。 |
国民負担率について 10月某日 晴れ |
「五公五民」という言葉がある。
収穫した農作物のうち、半分は自分に、残りの半分は年貢として納める制度のことだ。江戸時代の中期ごろ、将軍で言うと吉宗のあたりからこの比率が定着していたという。藩によっては公の取り分がもっと多いところもあった。手取りが半分やそれ以下になれば、さすがに農民も怒る。だから一揆も起きた。
それから200年くらいが経って、令和における年貢は税金と社会保険料になった。今年の国民負担率を見たら47%ほどである。そろそろ一揆が起きても不思議ではない水準だ。
税金や社会保険料の議論では、よく北欧型が例に挙がる。文脈としては、北欧諸国が福祉国家たる所以は6割とか7割とかに至る国民負担率であり、日本も少子高齢化と人口減少が止まらない以上、そういう道を目指した方が良いのではないか、という話である。
考え方としては間違っていない。国民の約3割を占める老人を支えるなら、彼らを手厚く支援する必要性はどれくらいあるのか、自己責任論において彼らの経済的な自助努力が足りなかった結果ではないか、といったそもそも論はいったん横において、現実的な手段として税金と社会保険料でお金を調達するのがもっとも確実で簡単である。そう考えると、なんとなく納得してしまう。
ただ、徴収したお金の使い道はどうなっているか。お金は流れ続けているものなので、入口だけでなく出口も見ないといけない。
その視点で見ると、例えば、北欧諸国は大学まで教育費が無償だ。デンマークなど医療費が無料の国もある。集めたお金の出口が機能しているから国民負担率が高くても納得度が高まる。これは経済的にも良いことで、福祉や教育に使うためのお金がその他の消費に流れるから経済が活性化する。
翻って日本はどうかというと、学生の半分が奨学金の返済に追われている。あらゆる給付に所得制限をつけて出し渋る。つまり入口に対して出口が小さく、入っているはずのお金がどこかで止まっている。簡単にいえば取られ損である。それを国民が実感を伴ったうえで理解しているから「増税メガネ」という批判になる。
30年のデフレ、未婚率の上昇、少子高齢化、人口減少、幸福度の低迷など日本が抱えるあらゆる問題は、その根本にこの取られ損の構造がある。根本にあるということは問題が根深いということだ。果たしてこのままで日本の未来は開けるのだろうか。国民負担率が1%上昇すると、国の成長率は0.3%低下するらしい。 |
人口減少について 9月某日 晴れ |
日本は少子化で、人口が減っているという。
東京で暮らしていると実感が薄いが、実際、子供の数も人口も減っていて、推計をみると、40年後の日本の人口は9000万人を割り込むらしい。
9000万人がどういう数字かというと、現在の人口が約1.2億人であるから、約3割の減少である。また、国の成長の重要な資本である労働力人口は現在の7000万人から4500万人に減る。労働力人口(4500万人)が人口(9000万人)の2分の1であるということは、働く手1人が2人分の労働価値を叩き出さなければならないということだ。
9000万人という数は昭和25年(1950年)の水準である。当時は戦後の復興に向かっていたため、直前の第一次ベビーブームでは出生率(合計特殊出生率)が4以上もあった。1人の女性が4人の子供を産むという状態で、そこから1.2億人の経済大国になった。
現在の出生率は1.3である。つまり親世代から子供世代に変わることで夫婦2人が平均1.3人になるわけで、人口は急ピッチで減っている現状はむしろ当然の結果ともいえる。人口を維持するためには2.07(人口置換水準)が目安で、データを見ると、実は第二次ベビーブームが終わる70年代からすでに人口減少の傾向は始まっていたようだ。
ベビーブームの時は出生数が増えて若い人が増える。戦後から1950年くらいが団塊ジュニア、70年前半が団塊ジュニア世代が生まれた時期であり、それぞれの時期で出生数が上がっている。出産には適齢期があるため、モメンタムで見れば、団塊ジュニア世代が結婚する2000年くらいに団塊ジュニアのジュニアが生まれて再び若い人が増えるはずなのだが、実際はそうはなっていない。表面的に見れば、団塊ジュニア世代が子供を産まなくなったことが今の少子化と人口減少の大きな要因だ。
子孫を残す、または残そうとすることが生きものの本能であるとすれば、子孫を残さない選択をすることは生物的に異常な行動であるともいえる。子供を産まない、子孫を残さないといった選択をする(または、せざるを得ない)理由としては、晩婚化、未婚、子なし婚などがあり、さらにその背景として、収入の不安定化、社会的ストレス、共働きの増加、子育て環境の複雑化など社会変化もあるだろう。それらが生きものとしての本能的な選択と行動を邪魔しているとするなら、少子化や人口減少の対策は政治家ではなく生物学者や社会学者の領域なのかもしれない。ダーウィンが生きていたら、日本の人口減少の根本的な原因を突き止め、もしかしたら効果的な解決策を提示したのではないか。 |
気候と社会と消費の変化について 9月某日 晴れ |
エコという言葉が浸透しはじめたのは20年以上前のことである。
企業側ではトヨタがエコカーを作りはじめ、消費者側では環境コンシャスな人(当時は変わった人だと思われていたところもあった)がエコバッグを使い始めた。今では新車に占める各種エコカーの比率が半分以上になり、日常的にエコバッグを持ち歩くようになった。世の中を後追いする法律に関しても、エコカー減税や有料レジ袋が消費行動の一部に組み込まれるようになった。
エコの浸透は社会課題の変化である。モノがなかった時代はモノ不足そのものが社会課題であったため、大量生産と大量消費がその解決策となり、安くて便利なものが売れた。しかし、モノがひと通り行き渡ると、大量生産、大量消費、そして大量廃棄による環境汚染が新たな社会課題になった。
この流れの中で、消費者側は商品などが作られる背景や、企業のCSR分野の取り組みを踏まえて、商品やブランドを選択するようになった。これをビリーフ・ドリブンという。価格と便利さが判断基準だった消費行動にソーシャルグッドの考えが反映されるようになったのは大きな変化だ。
一方の企業側も顧客志向から社会志向へと変わり、売上の一部を環境保護活動に寄付したり、原料や生産工程の透明性を明らかにしたりするようになった。近年では気候変動やエネルギー問題を中心とする環境関連だけでなく、生産や輸送などのサプライチェーン上の人権問題や、フードロスを含む食料問題なども消費や購買に影響するようになった。
ソーシャルグッドという点では、若い人たちほど環境や人権といった社会課題への感度が高いといわれる。代表的なのがZ世代で、彼らは環境問題が注目されはじめた時期に生まれ育ち、学校教育でSDGsなどについて学んでいる。
彼らが今後の消費の主体となることを考えれば、SDGsの時代においては今後も社会課題が消費に影響する傾向は続くはずで、環境や人権などを無視して作られる商品は売り場から弾き出されていくだろう。これは企業や人も同じで、社会志向の意識が欠けることによって存在感や居場所を失う。ブラック企業の淘汰はその一例で、今後はソーシャルグッドであることが当たり前になり、どれだけ積極的に社会課題の解決に取り組んでいるかが勝ち組と負け組を分けるようになるかもしれない。
それにしても今年は暑い。立秋はとうに過ぎ、9月は暦の上では秋のはずだが今日も東京は30度を超える「真夏日」である。これもエコ意識が高まる要因だと思う。地球温暖化の深刻さが、うだるような暑さという実感を伴うことによって深く理解されるようになったのだと思う。 |
思考の偏りについて 9月某日 晴れ |
日本は格差が小さく、義務教育制度も整っている。
これは人の思考が健全に成長し、成熟していくための重要な要素であり、日本が世界に誇れる一面であるとも思う。ほとんどの人が一定水準以上の知識や道徳を身につけることができるのも、外国と比べて日本が社会情勢的に安定しているのも家庭環境と教育制度によるところが大きい。
ただ、全員が常識的な人に成長するわけではなく、一般的な常識や教養を持ち合わせない困った人も少なからず存在している。福島県沖の処理水放出に反対している人たちが分かりやすい例だと思う。処理水の放出が科学的に見て問題ないことは学校で学ぶ程度の知識がある人なら理解できるはずである。むしろ原発由来の負の遺産を一手に抱えてきた福島が、10年超に及ぶ呪縛から解放されるという点で、処理水の放出は復興に向けた大事な一歩ともいえる。
困った人たちはそういう背景を理解せず、非科学的な感情論で不要な風評被害を生み出して復興を邪魔する。そういう人を世の中では左巻きとかリベラルと呼ぶ。オールドメディアにもそのタイプが多い。
困った人たちに共通しているのは、思考が偏った状態で固定されていることだと思っている。人が成長していく過程において、いったん左側に振れることはよくあることだ。それは反抗期や思春期によるもので、親や学校や制度などに反発するようになる。
ただ、それは「はしか」のようなもので、年齢とともに知識や経験が増えることで偏った思考は真ん中らへんに戻る。親や教師のおかげで自分が存在していることを認識したり、大きな体制の中で恩恵を受けていることに気付いたり、他者を思いやる利他的な心が芽生えたりして尾崎豊的な思考が自然と修正される。
思考のかぶれと修正までの一連を成長とするなら、困った人たちは思考が未熟な状態で止まっているため、引っ張りすぎたバネが戻らなくなるのと同じように、あるいは、意固地になりすぎて引くに引けなくなったのかもしれないが、何にでも脊髄反射で反対する。反対する理由はもはやどうでもよく、反対することが目的になっているようにすら見える。要するに、手段が目的化している。
社会はいろいろな人を受け入れる大きな器であるから、困った人だといって弾き出すわけにはいかない。その環境において重要なのは、彼らに社会活動の足を引っ張らせないようにすることであり、そのための具体的で有効な最適解は「相手にしない」ことだと思う。幸いなことに、現実社会においては、困った人たちの歪んだ主張はだいたい既読スルーされる。多くの人は、困った人に対しては距離を置くことが最適解であると判断する賢さがあり、これも日本の高度な教育制度の賜物だと思う。 |
透明性の時代について 9月某日 晴れ |
ウソも隠し事も全て明らかになる時代だ。
大手中古車チェーンの悪事が次々と暴かれ、一方では大手芸能事務所のパンドラの箱が開いた。この2つのスキャンダルから分かるのは、世の中の透明性が格段に上がったということだろう。
透明性を構築したのは、社会的にはコンプライアンスの浸透であり、生活環境的にはスマホとSNSの普及である。スマホさえあれば誰でも企業の内情や身の回りの出来事を発信でき、ネット市民として受信できる。悪事千里を走るという歴史の教訓にあるように、悪い情報ほど速くSNSで拡散される。そういえば、豪華なフランス旅行の様子をSNSにあげて炎上した議員もいた。あらゆる情報は良し悪しを問わず明らかになる。正直者がバカを見ることのない健全な社会に変わっていくために、この変化はとても良い変化だと思っている。
もう1つ良い変化だと思うのは、マスコミの存在価値を見直すきっかけになったことだ。大手中古車チェーンの悪評がSNSで広がっている中でも、マスコミは連日のようにこの会社のCMを流していた。マスコミにとってはスポンサー料が収入源の1つであるため、CMを打ち切ることができなかったのだろう。その気持ちも分からなくはないが、お金儲けのためのCMのせいで被害者が増えたかもしれない。その時点ですでにマスコミの存在価値はかなり低い。
芸能事務所に関しても、闇を闇のままにしてきたのはマスコミである。故人である事務所の元社長については、すでにタレントへのセクハラの真実性が最高裁で認められているが、その後も20年にわたって闇を奥深くに葬ろうとしてきた経緯がある。
情けなく感じるのは、セクハラ問題を取り上げたのが海外のメディアだったということだ。BBCが動かなければおそらく今も事務所のガバナンスは機能せず、ほぼ身内関係のマスコミとも共依存し続けていただろうと思う。マスコミとスポンサーの関係性についても同じことが言える。
過度の癒着は政治の暴走にもつながる。マスコミはしばしば「権力の監視」の役割を持つといわれるが、その役割についての評価をみると、アメリカが45%、イギリスが42%、韓国ですら21%であるが、日本は17%だという。また、同じことをジャーナリスト側に聞くと、日本では91%が権力の監視はマスコミの重要な役割だと答えている。この数値の差を見るだけでもマスコミ側と世の中の間で評価に大きな乖離があることが分かる。言い換えれば、すでに多くの人がマスコミをその程度の存在だと認識しているということである。 |
本性について 8月某日 晴れ |
国民的アイドル(元)の不倫報道を見た。
率直な感想は「ああ、そういう人だったのね」である。
「そういう人」とは何かというと、倫理観によって抑制されている向こう側に、その人の本質や本能や本性がある、ということである。
人は生まれた時から倫理を理解しているわけではない。むしろ生まれた時は動物的で、思考の奥底に汚れた願望を抱えている可能性すらある。
ただ、育っていく過程で倫理的な善悪を学ぶ。例えば、暴力はいけない、嘘をついてはいけないといったことを学び、その意味を理解することによって自分の言動をコントロールする生き物へと変化していく。この過程を世の中では教育と成長という。
いい年した人が倫理的観点における善悪の境界線を越えるのは、教育不足か、成長していないかだろう。そう考えると、彼女は倫理観が薄いといわれる芸能界で育ち、全国規模でチヤホヤされ続けてきたという特殊な環境で育ってきたこともあって、教育と成長の部分で不完全なところがあったと推察できる。
倫理的な善悪は、酔っ払うなどして自制の役目を担う前頭葉が一時的に機能しなくなった時にも間違う。これは老害が老害となるケースが分かりやすい。老化によって前頭葉の機能が低下し、自分の言動のコントロールが効かなくなって、その人の本質と本能が表に出る。
難しいことを言っているようだが、実はシンプルである。人はそもそも聖人君子ではなく、倫理観によってコントロールする言動によって聖人君子のように生きることができる。大事なのは、自分の中にどんな欲望があるかを自分で知っておくことで、己を知るといったソクラテスも、おそらくそういうことを言っているのではないか。
自分の中にある欲望は、普段は倫理観によって抑えられるため、通常は不適切な言動として表には出ない。他人からも見えない。
ただ、ふとしたタイミングで表に出る。その時に、その人の本性が他人から見えるようになり、「そういう人」なんだな、と思われる。
ところで、不倫は「不」と「倫」の熟語であり、倫理的な配慮が不十分であり、倫理観に不具合があることを意味している。倫理に外れる言動は恋や愛や性だけに限らない。しかし不倫という言葉がこの分野でのみ使われるのは、おそらくだけど婚姻関係における背信が人としての倫理を最も大きく外れた行為であることを示しているのだと思う。 |
多様性時代のスキルについて 8月某日 晴れ |
「そういう人」の続き。
人の価値観の多様性は、想像をはるかに超えて多様である。
とくにコロナ禍以降は、ワクチンを打つかどうか、マスクをするかどうかといった点で個人がそれぞれの価値観に基づいて行動することが前提になり、多様であることの価値が一段上がった。
人はそれぞれの考えを持って行動している。それは当たり前のことだが、多様であることを前提とする世の中においては、全ての人に理解されることはできず、逆に全ての人を理解することもできないのだとあらためて気づく。
話せば分かるというのは詭弁であり、それはロシアや中国政府を見ていれば分かる。話が通じないから戦争になる。
厄介なのは、政治や戦争とは関係がない日常生活においても、人並みに社会生活を営んでいこうとする過程で自分と価値観が異なる人と接点が発生することである。例えば、上司や部下や学校の先生や近隣の住人などは簡単には接点を解消できない。そういう相手と価値観が異なる場合、下手に踏み込まず、容易に踏み込ませない落とし所を作らないと仕事や日常生活に支障が出る。接客業などは一期一会の要素が強いが、自分の価値観のみで理不尽な文句をつけてくる人が何人もいたら、仕事が嫌になるだろうし精神を病むかもしれない。
それを避けるための最適解が「そういう人」と理解することである。多様性の時代において、「そういう人」と理解する力はストレスなく生きる処世術であり、人間関係を心地よく維持していくためのスキルである。
このスキルが身につくと、自分と全く考え方が異なる人と遭遇してもストレスにならない。むしろ、一歩引いたところから無数の変な人たちの変な言動を楽しむことができるようになる。
言い換えると、何でもかんでも相手の言うことに突っ掛かり、自分の主張を押し通そうとする人は「そういう人」と理解する力が欠けているということである。Twitterを見ていると、たまにそのタイプがいる。彼らは実社会でも同じように自己主張するのだろうか。それとも匿名になった時に強くなるのだろうか。いずれにしても「そういう人」と理解するしかない。
多様性を尊重しよう、相手を理解して受け入れようなどというと、なんだか難しそうに聞こえるし、実際に難しい。しかし、相手の考えの中に自分と合わないところがあった時に「そういう人」と理解するのは簡単である。そう思うことで相手の存在を認めることができる。これは実は多様性の第一歩である。
|
センスの価値について 8月某日 晴れ |
AIの進化が世の中の職業を大きく変える。
これは以前からよく言われていることで、野村総研とオックスフォード大学がまとめたレポートは、AI導入によって10〜20年以内に日本の労働人口の49%の仕事がなくなると言っている。(2015年12月のレポート)
AIに代替されるといわれている具体的な職業は、事務職、接客、小売店販売、運転、警備などで、その他の業種においても、単純作業に近い仕事から順番にAIの仕事に変わっていく。レポートが注目されてから8年ほど経ち、コロナ禍によってデジタル技術の普及スピードが早くなり、街中では対面前提の小売店などが減り、職場の様子も着々と変わっている。
生成AIが普及すると、代替可能性がある職業の範囲はさらに広がる。物書き商売も人ごとではなく、むしろ物書き商売は生成AIと親和性が非常に高いと思っている。親和性が高いということは、代替可能性が高いということだ。
物書き商売は、取材や勉強や雑談や日常生活の経験から得た情報(非構造的なデータ)から文章を作り出す仕事である。これはまさに生成AIの特徴だ。Chat GPTを見れば分かるように、生成AIはどこからか情報を引っ張ってきてコンテンツを生成する。ビッグデータを知識と経験の集合体と考えると、それを踏まえてコンテンツ生成する流れは人間的であり、人間の脳に近い。
また、物書き商売は正しい文章を書くだけでなく、読み手の共感や納得感を得られる面白い文章を書く力が求められる。AIが正確性、生成AIが共感や納得感の部分を担うことで、今後はAIが正確で感覚的にも優れた文章が書けるようになる。
感覚的な表現を代替できるという点で、生成AIは絵や音楽の作り手にとっても、服飾や建築といったデザインの仕事に就く人にとってもディスラプティブな技術といえる。恋愛はまさに感覚に基づく行動だが、最近はマッチングアプリで出会う人が多いらしい。これもデータと感覚の成せる技だ。属性など(データ)と好み(感覚)を組み合わせることで高度なマッチングができる。すでに家や仕事探しはデジタル化されているが、あらゆるマッチングはAIによって高度化すると思うのでマッチング業も代替される。採用や投資といった経営判断も、根拠に加えて経営者の感覚が重要であるため、今後は会社の意思決定もAIが担うようになるかもしれない。
生成AIがディスラプティブである理由は、「センス」という曖昧な言葉を情報の収集と組み合わせの仕組みによって明らかにし、代替するところにあるのだと思う。その結果、芸術的要素として認知されてきたセンスがコモディティ化し、センスという特殊能力で成り立っていた職業が代替される。そのような時代で人はどこで価値を生み出すか。その解をもつ人が社会に必要な存在として残るのだと思う。 |
賢い人について 8月某日 晴れ |
賢い人は勉強している。
勉強は、教科書的な勉強だけでなく、人と会う、話す、見る、読む、失敗や成功などを経験するといったあらゆる行動を通じた学びを含む。それらを通じてインプットが増えることによってアウトプットも洗練される。
ただ、インプットの積み上げだけが賢さではない。そもそも脳はインプットした情報を全て記憶するわけではない。例えば、街を歩いていると多くの情報が目や耳や鼻に入るが、脳に記憶されるのはそれら膨大な情報のごく一部だ。可愛い女子大生がいたとか、美味しそうな焼き鳥の匂いがしたとか、それくらいのことしか覚えていない。そこが脳とAIの違いでもある。AIはメモリを増やせばあらゆることを記録するが、脳が記憶できることには限界がある。
その限られた情報から、何かを考えたり、何かしらの法則性を見つけたりすることも賢さである。ニュートンは、リンゴが落ちるのを見て万有引力を発想したという。一般論として、記憶力に優れている人は想像力が弱いと言われる。頭にインプットされる情報の量に頼らず、1つの事象(リンゴが落ちる)から想像的な発想ができることも賢さであり、これは社会では地頭の良さという。
ニュートンは賢い人だが、偏差値で比べれば受験生の方が高いだろうし、棋士と将棋で勝負すればおそらく負ける。ニュートン的な賢さとは別の基準で、受験生や棋士が賢いと評価される世界があり、賢さの評価には複数の基準がある。
また、脳はAIではないので、適度にフィルターがかかった適量の情報だけが脳に記憶される。このフィルターの性能が良いほど、無駄な情報が少なくなり、大事な情報が優先的に脳に記憶される。頭に蓄積される情報の質が高くなる。すると、情報の処理がラクになるし処理のスピードも速くなる。このスピードのことを頭の回転の速さという。これも賢さの1つである。
重要な情報を絞り込むフィルターは五感で入手している。つまりインプットの量に頼らない賢さは、五感をうまく使うことによって構築される。また、五感を働かせるためには、道端に落ちているような情報ですら何かしらの学びになるという学習意欲が重要だと思っている。また、その情報を拾い上げるための集中力をコントロールすることも重要だ。
何かを学ぼうと思って集中している時は情報が脳に届きやすくなる。私の仕事を例にすると、取材で聞いたことや本で読んだことをよく覚えているのは、意識の面で学びの準備ができているからである。言い換えると、それ以外の場面で見たり聞いたりしたはずのことをほとんど覚えていないのも意識の問題であるということだ。ぼーっと生きているなあと改めて思い知らされる。 |
酷暑と蚊について 8月某日 晴れ |
今夏は1匹も蚊を見ていない。
その理由は、どうやら酷暑にあるらしい。本当かどうか分からないが、そうかもしれないと納得してしまうくらいに今年は暑く、ゴーヤのグリーンカーテン程度で対応できるレベルを超えている。
仕事部屋は朝から夜までエアコンを入れっぱなしである。私が寝床にしているリビングは、何度かエアコンを消して寝たことがあったが、毎回のように明け方に汗だくになって起きるため、良質な睡眠を確保するために夜通しでつけている。
エアコンを消して寝る時よりも辛いのは、仕事で取材などに出る時である。そういう時、私は基本的にスーツである。しかも、社長など偉い人で相手であることがほとんどなので、ネクタイあり、上着あり、マスクありのフル装備である。灼熱地獄とはおそらくこういう状態なのだろう。駅までたどり着く途中で命の危険すら感じることもある。
取材の往復時に周りを見ると、蚊すらいない酷暑をフル装備で移動している人はほとんどいない。ならば、我慢比べは私の勝ちである。私は案外、体力も精神力も強い。
ふと思えば、蝉の鳴き声も今夏はあまり聞かない気がする。来年以降も酷暑が続けば、天然のカブトムシを見たことがない子供が増えたように、何十年かしたら、天然の蚊とかセミを見たことがない子供が増えるのではないか。スーツでネクタイという格好が古き良き時代の服装になる日も来るかもしれない。ダーウィンはおそらくそういうことを言っている。コンクリートで覆ったヒートアイランドは、人間ですら不快に耐えながら生きているのだから、人間以外の生き物にはかなり住みづらいのだろうと同情すらする。
同情という点で、公園とか川っぺりなどで「蚊がいる」「虫がいる」と騒ぐ人がいるが、あれは虫が気の毒だと思っている。人の家にお邪魔して「この家には住人がいる」という人はいない。それと同じで、虫には虫の住処があり、そこにお邪魔している人間に文句を言われる筋合いはないと思うからである。逆に、家に虫が入ってきた場合には丁重に出て行ってもらう。家は人の住処であり、虫を招き入れた覚えはないからである。
この住み分けを理解することが、きっと自然との共存を考える際の基本的な姿勢なのだと思う。共存は、同じ場を共有することではなく、そこに必ずしも仲良しの要素を含む必要もない。命あるそれぞれの個体が、自分の居場所を平等に持てる状態のことであると思う。
|
ルールメイクについて 7月某日 晴れ |
世の女性たちは、男という生き物に油断し過ぎではないだろうか。
私は男だから、男がどういう生き物なのかよく知っている。簡単に言えば、男はエロくて野蛮な生き物である。年齢、見た目、肩書き等は関係なく、全ての男には性欲があり、機会さえあれば満たそうとする。そこに性善説は通用しない。
さらに言えば、自分は女性の味方だとか、女性を理解しているとか、自分にはもう性欲はない(消えた)などと言う男こそ疑った方がいい。彼らはほぼ間違いなく淀んだ性欲を抱え、その欲望を満たすための手段として仮面をかぶっている。それくらいの警戒心を持って接しないと、心を許した瞬間に襲われる。
そういう前提で考えない限り、性が関わる問題では間違いなく女性や女子が被害者になる。トランスとトイレの問題はその一例である。
この件に関しては、トランスの女子トイレ使用を制限することが違法(≒トランス男性は女子トイレを使ってよい)という判決が出た。だいぶ問題があると私は思うし、世の中にもそういう声が多いが、最高裁の判決にその上はない。
なぜこうなったかというと、男が決めたからである。
性に関する問題を考える場合、被害者になりうる女性のみでルール決めしないと意味がない。女性が主体性を持つことが大事であり、その意思決定においては、加害者になり得る男を排除しないといけない。
これは外国人の参政権の話も同じだ。日本に帰属せず、将来的に敵国となるかもしれない国に属する人が日本の未来に関わる政治に1票を持てるようにする制度案が意味不明であるように、女性の未来の安心と安全を脅かすかもしれない男が、その仕組みづくりに関わることがおかしい。
そもそも男側から見れば、トイレ使用がどう決まろうと、損するのは女性だと分かっている。だから真剣に考えないし、全力で頑張ろうともしない。全力でやる男がいるとすれば、前述の通り別の魂胆があるはずである。
もちろん、本質的に野蛮な生き物でも、日々の行動が野蛮になるとは限らない。それは理性があるからである。つまり理性>性欲であれば日常生活では安心して付き合える。しかし、いつ、どんなきっかけで理性<性欲になるかは分からない。本能や本質としてその可能性があるわけだから、そういう人を性的な面で女性が被害者になりうる課題の意思決定に関わらせてはいけない。そこに必要なのは多様な意見ではない。被害者になりうる人の意見である。
最高裁によってすでに蟻の一穴は空いてしまったが、なし崩し的に女性の安全が脅かされる社会へと落ちぶれていかないように、娘を持つ親として性に関わるルールづくりは女性が積極的になってほしいと切に願う。 |
多様性について 7月某日 晴れ |
思想の面でも行動の面でも、人のあり方が複雑になった。
発端はおそらくアイデンティティの話である。そこに人類の議論においてずっと根底なる權利と平等との話が加わり、多様性やインクルージョンの話も追い風になって、トランス概念というものが生まれた。
アイデンティティは大事だ。人は生まれながらにして平等に権利を持つし、インクルージョンを通じた多様性の拡大はあらゆる場面で生産性向上に結びつく。
1つ1つは正論なのだが、それらの組み合わせによって派生するトランス概念は違和感がある。その理由は権利と義務が表裏一体である前提に立っていないからだと思っている。
個を主張するなら相手の個を尊重しなければならない。また、多様性を主張するなら自らも多様な価値観を理解しなければならない。その視点と姿勢が欠けているから一方的な主張に聞こえてしまう。
これは不法滞在の外国人についても同じである。不法であるから退去が妥当という当たり前の話はおいておいたとしても、彼らは自分たちの保護や生活の保障を求めることだけに熱心で、義務を果たすという姿勢がない。意識としてはあるのかもしれないが、具体的な行動としては見えない。行動を伴わない意識は何もしていないのと同じだ。だから共感されないのであり、法治国家においては議論にすらならない。
社会全体では、政治や経営における女性比率を高めようという声をよく耳にするようになった。現状、政治家も会社の管理職も10%台が女性であるらしく、先進国水準で見ると低いので、世界に追いつこうという論旨である。
言いたいことは分からなくもないが、政治家も管理職も社会という大きな仕組みにおいては1つの役割に過ぎない。やりたい人がやればいいし、本気でやりたい人は努力してその役割を手にする。そのための自由は保証されているし、現状は男の方がそれら役割を手にしようとする熱意があるのだろう。
そう考えると、女性比率は結果に過ぎず、そこにKPIを掲げてもあまり意味がないと私は思う。単純な考えで50:50にすることにこだわると、やる気と能力がある人(この場合は男)に障害を設けることになり、結果として生産性は下がる。
トランス概念を間違って扱うと、そのうちに政治や経営に一定数のトランスジェンダーを入れようという話になるのではないか。それは多様性やインクルージョンの話とはかけ離れた施策で、勘違いでもある。
|
仕事の楽しさについて 7月某日 晴れ |
FIREという言葉が流行っている。
その背景には、「1日も早く仕事と縁を切りたい」という願望があるのだろう。
世の中には、仕事は楽しくない、仕事をしたくないと思っている人が一定数いる。もしかしたらそう感じている人が過半数なのかもしれないし、新橋あたりの飲み屋をのぞいてみれば、そう感じている人しかいないように感じるほどである。
ただ、一方には仕事が楽しいという人もいる。私の周りにはそういう人が多い。仕事が楽しく感じる理由は、楽しいと感じる仕事に巡り会えているか、楽しいと感じる仕事を見つけているか、あるいは今の仕事が楽しくなるような工夫をしているかであって、そこは運または努力が求められるところだ。
言い換えれば、何もせずに仕事が楽しくないとこぼすのはわがままだと私は思う。苦労せずにラクしたいという王様のような考えであり、王様だって外交とか内政とか命を狙われる恐怖とかでそれなりに苦労しているはずである。
仕事運が良い私は、幸いなことに仕事を楽しいと感じている。取材で会う人たちとの会話も楽しいし、その過程で発見したり学んだりできることも楽しい。社長取材では戦略の立て方や社会の変化の捉え方などが学べるし、投資関連の取材では相場の見方などについて学べる。
知る、学ぶ、気づく、分かる、そして、それらを生かして自分の人生をより良いものにするといったことまで含め、仕事は楽しい。仕事で学んだことを私の仕事や人生に生かせているかどうかは別として、知的好奇心の部分はかなり高いレベルで満たされる。
とくに最近は世の中が社会課題に高い関心を持っているため、環境や子供たちの未来に関わるテーマで話を聞いたり原稿を書いたりする機会が増えた。私は、あらゆることを若い人を起点にして考えるし、頑張っている若い人を応援し、困っているならできる範囲でお金も時間も提供する。物書き仕事を通じて多少なりとも若い人たちの未来を良くすることに貢献できていると思うと仕事はなおさら楽しくなる。
仕事は、仕事そのものだけを切り取ってみれば単なる作業であり、そこに楽しさは存在しない。しかし、その仕事が誰のどんなことに役に立つかまで想像すれば、仕事をする意義が見えて楽しみも感じやすくなる。
きれいごとを言っているわけではない。それがおそらく仕事との正しい向き合い方である。人生の半分くらいを仕事に費やしていくうえで、仕事に意義を感じられるかどうかは人生を楽しむという点で非常に大事だと思う。
|
運について 6月某日 晴れ |
運の良さには自信がある。
今の自分が楽しく毎日を過ごせているのは、そのほとんどが運によるものであるとすら思っている。ありがたいことである。
ただ、運にも金運とか仕事運とかいくつかの分類があって、その濃淡はある。具体的には、私は仕事運と人との出会い運がずば抜けて良い。何の取り柄もなかった若造が物書き商売を続けていられるのは、良い仕事をもらい、また、良い仕事を与えてくれる応援者のような人がいるからである。
健康運の良さにも自信がある。私は小さい頃は入院したこともあったが、この20年くらいは風邪すらひかない。お腹も壊さないし、花粉症以外の持病もないし、たまにダルさを感じても、飲んで寝れば次の日には完全に回復している。
これは親に感謝である。子供の頃、私は8時か9時には寝ていた。睡眠によって胃腸も精神も強くなった。そう思っているから、我が子たちにもなるべく早く寝るようにと言っている。
一方で、金運はイマイチである。その原因は、そこまでがむしゃらに稼ごう、貯めようとしていないからであって、本気で取り組まないことには運もついてこない。言い換えれば、仕事運や人の運が良いのは、与えられた仕事に本気(自分なりに)で取り組み、周りの人を大事にしてきた結果である。
この因果を理解することは、運を味方にするための姿勢として大事だと思う。幸運に恵まれることを「棚からぼた餅」というが、ぼた餅を見つけるためには棚まで行く必要がある。ぼーっと座っているだけで棚の方から近づいてくることはない。お金に関しては、私はぼーっと座っている状態に近い。宝くじを買わずに宝くじが当たるのを期待するようなもんである。
出会い運は良いのだが、恋愛運は良くない。これも因果なのだろうと思う。
恋愛に関して、私は内心、面倒だなと思っている。人との距離感を掴むのが下手なのかもしれないが、その間合いについて考えることがすでに面倒だし、面倒なことは楽しくないので続かない。実際、仮に美人と恋愛できる機会に恵まれたとしても、私はおそらくその関係をダメにするだろう。私が恋愛運の配分担当者だったら(そんな担当がいるかどうかはさておき)、恋愛関係を育てる意欲も行動もしない人をみたら、「こいつに恋愛運を与えても無駄だな」と考える。だから私の恋愛運は良くないのであり、ここで大事なのは私はそれで構わないと思っていることである。
運について、松下幸之助さんは自分が運がいいと答えた人を採用したらしい。多少のバラつきはあっても自分は総じて運がいいと思えることは、それ自体が運を良くすることなのだと思う。 |
左右について 6月某日 晴れ |
政治の左右ではなく、日常生活における左右の話である。
私はたまに左右を間違える。右手側が右、左手側が左であることは分かっているが、不意に「左に寄って」と言われると右に寄ったり、右に曲がって欲しい時に「左に曲がって」と言ったりする。これは左右盲というらしい。私は軽度だがその傾向があり、歩いている時も間違えるし運転している時はさらに間違いが増える。
いつからそうなのか思い出してみると、思い出せないくらい昔からだと思う。左右盲という言葉を知ったのは最近だが、自分が左右の判断を間違うことが多いことは認識していたし、だからと言って、それで大きな問題が起きることもなかったので、そういうもんと思って生きてきた。
そもそも私は方向音痴であるが、これもおそらく左右盲と関係する。「あのビルを右、その先を左」といった指示を脳内再生しながら目的地を目指すが、どこかで左右を間違うため、気づけば逆方向に進み、目的地から離れている。
だから私は、仕事でも遊びでも待ち合わせの15分以上前には着くようにしてきた。最近はGoogleマップを見て歩くので迷ったり間違ったりすることがほとんどなくなったが、その点については自分を信用していないので、今も15分前行動が続いている。
Googleマップのようなテクノロジーはありがたい。一方、テクノロジーの普及による新たな問題もある。例えば、リモートの打ち合わせで資料を説明する時、私は高確率で左右を間違える。自分では資料の左にあるグラフを指しているつもりだが、「右のグラフにあるように……」などと説明している。
リモートで混乱しやすいのは、鏡の世界と混同しているからだと思う。鏡の中では左右が逆転する。右手を挙げると相手(鏡の中の自分)は左手を挙げる。その感覚があるから、資料では右にあるグラフも、相手から見れば左にあるのではないかと錯覚する。
左右を普通に判断できる人には意味不明の話だと思う。自分でも、どう説明するのが正しいのかよく分かっていない。重要なのは、そういう軽い混乱が頭の中で生じること、そして、考えれば考えるほど理解不能に陥ることである。
これは簡単には解決できないし、解決策も分からないので、最近は右と左をだいたい当てずっぽうで言っている。50%で外れるけど、間違っていたら相手が「言い間違えだろう」と解釈し、自分で修正するだろう、という感覚である。
先日、取引先の人とそのことについて雑談していたら、心配そうな表情で「上と下は分かりますか?」と聞かれた。
……分かるに決まっているだろう。 |
徹夜について 6月某日 晴れ |
最終的には気合いだと思っている。
令和の世の中で、何を昭和なことを言っているんだと思うかもしれないが、気合いは大事だと本心で思っている。
10数年ぶりに徹夜をしたのは今年の3月のことだ。以来、もう少し時間管理を丁寧にやらなければと考えて着々と仕事をこなしてきた、つもりであった。
それから数ヶ月経って、再び徹夜をすることになった。前回と異なるのは、2日連続の徹夜になったということである。徹夜をすると8時間くらいの業務時間を捻出できるが、それでは終わらない。そのため、翌日も日中仕事をして、その夜は2夜目の徹夜をして、さらにその次の日中も仕事をし続けて、ようやく仕事を終わらせることができた。結局、7時くらいに起き、その次の次の日の夜12時に寝たので、65時間ぶっ続けで仕事をした。
無謀なスケジュールだと思うが、やってみると案外眠たくならない。肉体労働でないからかもしれないが、1日目の徹夜明けも、2日目の徹夜明けも頭は冴えていた。ようやく寝た翌朝も気持ちよく目覚めたし、2日続けてお酒を飲まなかったため胃腸も喜んだのではないか。
私は体力に自信があるわけでもなく、軽度の運動すらしていない堕落した生活に浸かっている。それでも2徹夜の試練を耐え抜くことができた理由は気合いである。気合いをもう少し因数分解すると、やればできるという自信と、やらなければならないという責任感である。それが揃えば、やってやれないことはない。
私は常々、子供らに気合いが大事だと言っている。2徹夜を完遂して良かったことの1つは、気合いの大事さを身をもって伝えられたことである。
生きていれば辛い時はやってくる。八方塞がりの状態に陥ることもある。そういう局面を乗り切るため(できれば、そうならないため)のスマートかつ効率的な方法を教えるのが父親の役目かもしれないが、準備万端で万全を期して生きていても思わぬ難局に陥るのが人生である。
その場合でも、気合いがあればどうにかなる。そこで折れる人と折れない人を分けるのは気合いである。そんなことが伝わったのではないか。また、私は他人には努力している姿を見せない(それほど努力もしてないわけだが)が、努力することに重要性は知っているつもりだから、子供には見せる。そんなふうに思えば、2徹夜しなければならないような無茶なスケジュールもやる価値はあった。もちろん、もう1回やるかというと、やらない。今度こそ、時間管理を徹底しようと反省している。 |
情報について 6月某日 晴れ |
社会は多様な情報の組み合わせで成り立っている。
流行り廃りに関する短命の情報から命に関わるようなエッセンシャルな情報まで、情報の受け手である私たちは常に情報を追いかけて生きている側面があるように思う。
気づけば、情報は、ヒト・モノ・カネと肩を並べて、経営資源の一角を担うまでになった。一方で、情報が重視されるようになり始めた頃と比べると、情報の価値の捉え方が変化しているようにも感じる。
短期間だが、私は情報誌の制作に携わっていたことがある。今から20年前のことである。あの頃は世の中に情報誌がたくさんあった。それらが事業として成立したのは情報そのものが不足していたからである。美味しい店、最新のファッション、成功しているビジネスモデルなどについて知りたい人がいて、しかし、そのニーズを満たすツールや仕組みがなかった。情報の需要過多である。
その後、インターネットが普及して需給バランスが整い、スマートフォンで何でも調べられるようになって情報の需給バランスは逆転した。供給過多の状態になったことで情報の非対称性が極限までゼロに近づき、情報供給の手段が増えたことにより、取捨選択を通じて最もアクセスしやすいTwitterやInstagramなどのSNSが主役になった。
これらが特徴的なのは加工や編集された情報ではなく一次情報が多いということだ。そこに価値があるから、寿司チェーンなどでの客の悪事などが拡散し、社会問題になる。これは、情報の価値は鮮度とスピードにあると捉えられるようになったことの現れと言える。その視点で見ると、情報提供ツールの主役だった新聞やテレビなどマスメディアの影響力が下がった理由も分かる。これらメディアは鮮度とスピードに劣るため、SNSをなぞっているのが実態だからである。
情報は、いつ、どこで、誰が、何をしたかを伝えるもので、今やスマホさえあれば誰もが情報を集められる。情報収集力の差が小さくなるほど、情報通であることの価値も下がる。
5W1Hでいうと、いつ、どこで、誰が、何をしたかは「知る」ことであり、なぜとどうしては「考える」ことと区別できる。ここに情報活用のポイントがあると思っている。つまり、店のしょうゆボトルを舐める人がいたという情報を知っているかどうかではなく、なぜそうなるのか、どうすれば現場を良くできるのかを考える力が問われる。社会の中で、情報は考えるための材料として存在していると私は思っている。世の中に変化や変革をもたらす思考を促し、社会的に大きなインパクトを与えられる情報ほど情報としての価値が高いのだと思う。 |
お尻について 5月某日 晴れ |
お尻は魅力的である。
何て下品なことを言っているのかと思うかもしれないが、たまには下品な話もいいだろう。
異性に対する男の嗜好は二分されている。1つは胸、1つは尻。これは派閥みたいなもので、お互いに相容れることはほとんどない。たまに「胸も尻も」という許容度の高い人はいるが、普通はどちらかの派閥に属する。
さらに言うと、日本男児の場合はマジョリティは胸派である。この点はおそらく異論は少ないはずだ。グラビア類を見ても、女性タレントの人気要素を見ても、フェティシズムを前面に出す動画類を見ても、人気があるのは胸または胸をフィーチャーするものであり、ほとんどの男児の興味はその大きさや形や露出度合いにある。
それは分からなくはない。男には胸がないから、ないものに関する興味という点で、あるいは哺乳類として乳飲児から育った潜在意識の面で、異性の胸に興味が向く理屈と背景も理解できる。
ただ、個人的にはあまり興味がない。見てもいいなら見るが、積極的に見たいとは思わない。それよりもむしろ尻だと思っている。尻については、見てもいいなら積極的に見たいとすら思う、時がある、かもしれない。
なぜ尻なのかというと、自分でも分からない。これは辛いものが好きとかジェットコースターが好きとか、そういう分野の話であって、理性というよりは本能や変態性に近い部分だとも思っている。
そもそも尻とは何かというと、胸の場合はアンダーとトップの数値化によってここからが胸であると定義できる背景があるが、尻に関しては、背中と太ももの間みたいな捉え方であり、明確な境界線がない不思議な部位である。果たして私が尻と言っているエリアが尻なのかどうかもわからない。
この曖昧さは、国境のような絶対的な境界線が定義されていない分野に向けた補助線であり、そこに関心を向ける重要性を示唆するものでもある。仕事の領域、人間関係、環境問題、政治の責任なども境界線が曖昧であるため、尻への関心を高めることは、その純粋な変態性を応用することによって数多くの社会課題の解決につながる可能性もある。
尻と関連してその話をしようと思っていたのだが、尻に関する何がどう社会課題の解決につながるのか忘れた。自分なりのロジックがあったのだが、思い出せないので、この稿は「尻は魅力的だ」と思っている尻フェチの下品な話として終わることにする。 |
タイパについて 5月某日 晴れ |
時間は本当に平等なのだろうか。
1日は24時間である。1年は365日または366日である。それは分かっているのだが、どうにも時間が足りない。
コロナ禍以降は特にそう感じる。自分の知らないところで時間が溶けている、または無意識のうちに時間を奪われている。そんな妄想さえしてしまうほどである。
コロナ禍以降の3年を振り返ると、経済的な余裕ができたおかげで地域や社会にお金を使えるようになった。それはすごくいいのだけど、一方で、仕事以外のことに目を向く時間が増えて、総量としての時間が減っている。
パーキンソンの第一の法則は、「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」と言っている。その通りである。実はやることの量ではなく、やることをこなすための時間管理に問題がある。1つ1つの仕事を処理する能力が低下して、余計な時間がかかっているかもしれない可能性も含めて、あらゆることを納得がいくまでやろうとするから、必然的に時間が足りなくなる。世の中には、仕事も家庭も面倒見ながら、余剰時間で趣味をしたりパチスロしたり恋人を作ったりする人もいるという。私は無趣味だし恋人もいらないが、適度にパチスロするくらいの時間が捻出できる時間管理の方法を学びたいとは思う。
最近はコスパの時間版としてタイパ(タイム・パフォーマンス)という言葉もよく耳にするようになった。時間あたりの効用や効率を考えて、例えば、映画を倍速で見て時短したり、結末やあらすじを知ってから映画を見るかどうか決めたりする人もいるらしい。
私は基本的には時間主義者だから、その考えにはとても共感する。ついにそこまで来たかという気がするし、自分の時短術をそろそろ更新しなければいけないという気もしている。
ちなみに、パーキンソンの第二の法則は「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」である。これも納得である。趣味をしたり恋人を作ったりする暇のないほどバブっているはずだが、手持ちのお金が増えていない現実を見るとそれがよく分かる。 |
物書きの契約について 5月某日 晴れ |
物書き商売は印税が収入源の1つである。
印税は、執筆した本の売れ行きに応じた収入が発生する仕組みで、例えば、1,000円の本で印税率が10%の場合、1冊売れて100円、1万冊売れて100万円、100万冊売れると1億円の収入が発生する。
私が担当している仕事が主に2種類あって、1つは社内報やイントラ向け記事など、もう1つは本の執筆や執筆協力だ。その中に株や投資の本も含む。
前者は印税が発生しない単発の仕事である。前者は業界的には印税が発生することが多いが、私は印税契約ではなくて1冊あたりいくらという手間賃の契約が多いので、印税をもらう機会はほとんどない。
契約方法は出版社によって異なるので、「印税契約で」と言われればそうする。ただ、本音を言うと私は印税をもらうことに違和感がある。
その理由は、本が売れるかどうかは私の努力よりも出版社に属する販促や広告や営業チームの努力によるところが大きいため、他人の努力によって生まれた印税を分けてもらうことになんとなく後ろめたさを感じるからである。
昨年は、印税契約は2件だけだったと思う。その本は売れたから、もしかしたら他の本の仕事も全て印税契約にした方が儲かるかもしれない。
ただ、その可能性を考えるより、後ろめたさなく仕事ができることの方が私にとっては大事である。これは考え方の話で、好みの話でもあり、要約すると、本を作る部分は責任を持ってやりますけど、売れるかどうかについては知らないよ、という話である。
少し見方を変えると、印税はサステナブルである。今年の仕事が来年以降の収入安定につながる可能性がある。一方の単発型は、単発の仕事の積み上げでありPL的な発想である。
そう考えると、持続可能性が問われる今の世の中において、現状の私の契約形態は前時代的である。実際、私が倒れたら、その瞬間から収入が止まる。健康と寿命の観点から見ると、PL的発想はかなりリスクが高いと改めて思うし、20数年に渡ってよく生き延びてきたなあとも思うし、後追いの副収入となる印税がないから時間に追われるのだなとも思う。 |
不確実性の許容について 5月某日 晴れ |
ギャンブルに対する反応は二分される。
私はギャンブル容認派であり自分が思考パターン的にギャンブルを好むことも認識している。一方にはそういう生き方を毛嫌いしたり目の敵にしたりする人もいる。パチンコはダメ人間がするもの、競馬は身を滅ぼすなどと信じて疑わないタイプの人である。
そっち側に片足を突っ込んでいた(いる)立場として、この指摘は間違いではないと思う。ただ、ギャンブルに酔心することもそれを否定することも、いずれも思想の類であるから、どっちでもいい。
気になるのは、このような思想の差が生まれる背景である。
経験則として、男女差は影響していると思う。私が知っている女性は、そのほとんどがギャンブル否定派である。ギャンブルで身を滅ぼすのもたいてい男性であり、脳の構造などが違うのだろう。
一方で、日本人の国民性としてギャンブルに対して否定的であるという説もある。それを表しているのがホフステッド指数である。
ホフステッド指数は不確実性を回避する傾向を数値化したもので、数値が高いほど不確実性を避ける傾向が強いことを表す。この文脈における不確実性はリスクやギャンブルと言い換えても良いだろう。
国別で見ると、アメリカが46、中国が30であるのに対して、日本は92で飛び抜けて高い。これは日本人らしさをあらゆる面で説明する。
米国人は資産の約半分を株などのリスク性資産で持つが、日本は預貯金で持つ人が大半である。最近は変わりつつあるが、日本は海外と比べて転職率も低い。起業率も低い。これらは不確実性を伴うからだと説明できる。つまりギャンブルを否定する人は日本人的であると言える。
グローバル化において転職や起業が投資が珍しいものでなくなれば、それが次世代の日本人の思考を変えてギャンブル否定派も減るかもしれない。
投資とギャンブルを同列で語るな、キャリアはギャンブルではないといった声が聞こえてきそうだが、私はその違いがよく分からないし、不確実性という言葉でくくれるのであれば大差ない、または同じと見て問題ないと思っている。世の中には確実なものもある。ただ、確実なものばかりに囲まれて生きるのはつまらないと思う。あるいは過去の経験や今の仕事を通じて不確実性に鈍感になっているからかもしれない。 |
アジャイルの限界について 4月某日 晴れ |
アジャイルと物書き商売のプロセスは合わない。
この1週間(1ヶ月くらいかもしれない)、最初に出した原稿(初稿)の修正に追われている。修正は、普段はほとんどない。私は基本的には納期を守るので、納期が重なると初稿の質が下がるのだろう。
修正がくると、手が止まる。私はそもそも修正が嫌いなのだが、やらないわけにもいかない。そのせいで次の仕事の納期が遅れる。修正に時間を取られるので次の仕事に着手できない。その循環のせいで次の仕事の初稿の質が下がり、また修正がくる。そのせいで次の仕事の初稿が、という悪循環にハマりかけている。
根本的な原因は、バブっているからである。私の納期管理の問題もあるが、もっと根本的な問題として、周りが大体バブっている。だから、うちに完成度6割くらいの企画書が来る。それが二転三転するので修正が増えて、お互いに工数が増える。
もう一歩踏み込むと、依頼が来た時点で「これ、二転三転しそうだな」と分かるから、こちらも初稿にこだわらずにアジャイルでやろうって思っちやう。アジャイルというと聞こえがいいけれど、要するに熟考せずに仕事が進み、修正が増えていく。
アジャイル的な作り方はシステム開発とか新規事業の創出にはいいのだろうけれど、もの書き商売にも応用できそうと思ったら手戻り多くなるだけだった。
感覚的には家作りに近いかもしれない。設計図が二転三転する状況で大工さんは家づくりに苦労するだろうから(もの書き商売は大工さんの仕事に非常に近い)。
お手伝いしいてくれる人を増やしたいのだが、歴史に学ぶとすれば、それをやるとバブル崩壊で人件費で詰む。
要するに、バブルに乗っているつもりがバブルに追われていた。それに尽きる。コロナ禍バブルが終わりそうな今、今一度アジャイルからウォーターフォール的な仕事のやり方に戻さないといけない。 |
仕事と物書きの本質について 4月某日 |
仕事の本質は困りごとの解決だと思う。
これは大筋、世の中に支持される考えだと思っている。自分がお金を払う場合を考えてみても、困っていることを解消してくれる誰かや何かが存在しているからだ。
例えば、自分では食料が作れないのでスーパーマーケットで食料を買う。取材や打ち合わせのために移動する必要があるので(最近はリモートが多いのでお出かけが減ったけれど)、そのために電車賃を払ったりガソリン代を払ったり。服もスマホも家も作れないので、そこで需要が発生してお金という対価が作り手に渡る。
今さらながらよくできた社会である。最近はこの仕組みがうまくできすぎていて、「金さえ払えばなんでもできる」と思い込んでいる人もいるが、そういう人はきっと困りごとには目が向かない。自分はなんでもできると思っている人ほど、実際は何にもできない。そのできないことをお金の仕組みで補っているだけの話である。それを自覚することは大事だと思う。
商売の本質が困りごと解決であるとするならば、物書き商売は誰に、どんなふうに役に立っているのだろうか。それがよく分からないから、この商売が成り立つ理由がよく分からない。
想像するに、何万文字という量の原稿を書ける人がいなくて困っているので、「じゃあ、誰かに頼もう」ということなのだとは思う。そう考えると、最近はAIが優秀で、ChatGPTにお願いすればそれなりの原稿ができる。
これは大きな変化だ。それなりの原稿しか書いていない人は仕事を失うことになりかねない。だって、ChatGPTはタダで困りごと解決してくれるわけだからね。
「タダより高いものはない」というが、記事の作り手がフリーライダーになったら物書き商売はごく一部の人を除いて成立しなくなるだろう。今後はフリーライター(ややこしいな)は儲からない、AIで十分などと考える人も増えるのではないか。それは物書きの本質を考えるきっかけになるだろうし、商売の面では、おそらく私にとっていいことなのだろうと思う。
それにしてもAIはすごいな。 |
信頼について 4月某日 |
確定申告の時期である。
今年の予定がそろそろ埋まりそうである。
何の予定かというと単行本の執筆や企業のアニュアルレポートのような大きな仕事の予定である。現状8月まで埋まっている。10月と12月も埋まっているので、9月と11月が埋まったら今年は予定表の上では終わりである。まだ新年度が始まったばかりだが、そろそろ来年の手帳を買いに行かなければならない。
私は基本方針として、文字数が7万字とか10万文字とかになるような大きな仕事は1ヶ月に1つまでと決めている。過去には「もうちょっとできるのではないか」と色気を出して月に2本引き受けたこともあった。コロナ禍バブルが始まった2020年の年末のことだ。その結果、1つ1つの仕事が雑になり、修正の戻しが増えた。手戻りが増えると次の仕事に手をつけられなくなりドミノ倒しを起こしそうになった。同じ轍を踏まないために、以来、1ヶ月1本、年に最大12本の予約制にすることにしたというわけである。
ただ、それでも締め切りが遅れる時はある。そういう場合は依頼者に相談である。あと3日くれないか。そうお願いすると、ほぼ間違いなく3日延ばしてくれる。人によっては1週間くらい延ばしてくれることもある。
こういう神対応はありがたい。快く(多分)延ばしてくれる理由は、私の周りに優しい依頼者が多いこともあるのだが、私自身の信頼も多少は関係していると思う。私が信頼されている、と言いたいわけではない。たまたまそうなっただけの話である。
私が物書きとして独立した理由は、締め切りを守る物書きが少ないと感じたからだ。ならば、締め切りを守る物書きは重宝されると考えてこの仕事を始めた。そして、その考えに従って、物書きをして20数年に渡って締め切りはだいたい守ってきた。
そういう実績が信頼につながっている。伊達が3日くれというのだから、くれてやってもいいじゃないかと思ってくれる。
物書きは文章力が大事だと思うのだが、依頼がくる本質的な理由は取材や執筆の能力よりも信頼だと思う。それが経営や仕事の根幹だとも思う。
依頼者目線で見ても、私に依頼してくれるのは「いい感じにやってくれるだろう」と思うからだろうし、私自身、依頼がくる理由は能力というよりは見た目によらず案外ちゃんとしているから、だと思っている。 |
生産性の限界について 3月某日 |
コロナ禍によって仕事の生産性が上がったはずである。
物書き商売を例にすると、コロナ禍による最も大きな変化はリモートが普及し、打ち合わせや取材のために現場を行き来する時間が減ったことだ。
コロナ禍以前は、30分の打ち合わせのために往復1時間かけてお客さんのところに行くといったことが当たり前に行われていた。今はその1時間を別の仕事に使えるようになり、従来であれば断らざるを得なかった仕事を引き受けられるようになった。これが物書き商売のバブルの始まりである。
もう少し掘り下げると、時間あたりの仕事の密度も濃くなった。打ち合わせや取材で外に出るとそれなりに体力を使うため「今日は頑張った」という実感が生まれる。達成感に浸って帰り道にコーヒーを飲んで帰る。人は頭を使って疲れた時よりも体を使って疲れた時の方が「今日は頑張った」という気持ちになりやすい。
今はどう変わったかというと、1日に何件かのリモート仕事が続いても動いていないので肉体的には疲れないし、移動がないから1つ仕事が終わったらすぐにでも別の仕事に取り掛かれる。肉体的な疲労を癒すためのコーヒータイム(サボりともいう)がなくなり、1日あたりの仕事の密度が濃くなる。
世の中全体についても同じことが言えるのではないか。接客やエッセンシャルと言われる職種のように人が物理的に現場にいなければ成立しない仕事は別だが、例えば事務とか営業などはリモートが普及したことで通勤や移動の時間が減っているはずである。出先や帰り際の小休憩なども減って時間あたりの密度も濃くなっているはずである。時間の効率化と時間あたりの密度の向上は、要するに生産性である。
不思議なのは、生産性は上がっているはずなのだが目に見える成果にはつながっていないことだ。GDPを見れば、満員電車に揺られていたアナログの時代(当時はPCやスマホなども普及していなかった)の方が成長率が大きい。今は成長率が横ばいであり平均給与も増えていない。そう考えると、生産性が注目される世の中だが、成長の本質はそこではないように思える。私なりの答えは生産性より生産力であり、つまり人を増やす、子供を育てることであり、仕組みや制度の面で子育てできる世の中に変えることだと思っている。 |
物書きの商売の疑問について 3月某日 晴れ |
物書き商売はなぜ成り立つのか。
たまに、よく20年も続けているな、どうやったら仕事が来るのかと聞かれることがある。しかし、理由は当人ですらよく分かっていない。仕事をいただくので引き受ける。それを繰り返していたら20年が過ぎていた。
業界を見渡すと廃業する人は多いらしい。なぜ廃業になるのか。他にやりたいことがあったとか、物書きに飽きたとか色々と理由はあるのだろう。「仕事をいただく、引き受ける」というサイクルが回らず、精神的や経済的に続けられなくなる人もいるのだろうと思う。
1つ言えるのは、本や雑誌が売れない時代だという人がいるが、そのような需給や業界環境の変化は実はほとんど影響しないということである。その点について、令和の知性であるChatGPTさんもこんなふうに考察している。
「ライターという商売については、将来的にも需要があると考えられます。なぜなら、情報化社会が進展するにつれて、書かれた情報の需要は増え続けるからです。また、企業や団体は、コンテンツマーケティングやSNSなどを活用して自社や商品のPRを行う必要があるため、ライティングの需要が高まっています」
需要が高まっているかどうかは分からないが、時代の流れや変化に関係なく、一定の需要があるという点は、その通りだと思う。
一方で、こんなことも言っている。
「ライターとして生計を立てることは容易なことではありません。競合が激しく、価格競争も起こり得るため、高品質なコンテンツを提供することが必要です。また、ライティングに特化するだけでなく、ビジネススキルやマーケティングスキル、テクニカルスキルなどを身につけておくことも求められます。
総じて、ライターとして成功するには、高い品質のコンテンツを提供し、幅広いスキルや知識を持つことが必要であると言えます」
要するに、物書きとして優秀でなければならないということだ。それが正解だとすると、物書き商売が成り立つ理由はぼんやりと見えたが、私が物書きとして成立している理由は謎である。 |
料理と原稿について 3月某日 晴れ |
ほぼ毎日、料理をする。
ほとんどが焼き物と炒め物ばかりだが、何を作るか考えるところから始まり、作る過程も、子供らと一緒に食べることも、美味しいと言ってもらえることも楽しいので、とくに苦労を感じることなく作っている。
料理には、切る、潰す、ちぎる、砕く、焼くといった破壊的要素があるため、それが多少のストレス発散にもなっている。そう書くと危ねえやつに見えかねないが、世の中には破壊して良いものがないが食材は別だ。日常生活では包丁を持ったり火をつけたりしてはいけないが、料理ではそれが普通で、料理の工程の必然性からマグロのサクを切ったり牛肉を炙ったりする。その工程が潜在的な破壊願望を満たしたり社会的な抑圧性を解消したりすることに結びつき、ストレス発散になるのではないかと思う(説明するほど危ねえやつの意見に見えてきたな)。
料理は原稿書きの仕事と似ているところもある。インタビュー原稿を例にすると、食材は相手の話で、面白い話はいい食材のようなものだ。物書きは、その食材を味付けする。そこに技術と経験が求められる。
優秀な物書きは、1つの食材を辛口の原稿に仕立てたり甘い話にしたり色々な味付けで料理できる。そのための調味料は勉強で身に付く。何気なく読んだ本でうまい構成や言い回しを知り、それが調味料として手に入る。
例えば、同じメッセージを繰り返してバター炒めのようなコッテリした原稿にしたり、主張を抑えたあっさり塩味の読みやすい原稿にしたり、といったことである。
インタビューに関しては、話し手である相手の人柄や性格をどう出すかも重要だ。これは出汁のようなもので、出汁が決まらないと原稿全体がまとまらず味わいが薄くなる。椎茸の出汁のように存在感がある人もいるし、昆布出汁のようにキャラクターの主張が控え目な人もいる。そのような違いを味わいといて原稿に反映させること、また、複数の出汁を使い分けられるのが物書きの能力であり、それは塩コショウの加減といった味付けよりも実は重要だと思っている。
最終的には感覚と積み重ねの話になるのかもしれない。料理では、いい感じの焦げ目になった、美味しそうな匂いがしてきた、ちょっと焦げたな、まだ固いかといった感覚が大事だ。それを毎日やっているから上手くなる。
原稿も似ていて、自分の書いた原稿を読み直してみると、読みやすい、リズムがいい、あっさりしすぎだな、ちょっとくどいなどと感じる。他の人が書いた本や原稿を読んでいる時も同じだ。その積み重ねで感覚が磨かれる。感性やセンスの有無ではなく、継続によって習慣化することで感性やセンスが発揮できるようになるわけである。
|
晩酌について 3月某日 晴れ |
かれこれ10年くらい毎日飲んでいる。
毎日ですか、と驚かれることがあるが、私はそこに驚くことに驚く。甘いものが好きな人は、食後のデザートを楽しむ。お茶やコーヒーが好きな人はそういうのを飲んで自分の1日を労う。映画やテレビが好きな人は、ソファでくつろぎながらそれらを観て1日の疲れを癒す。
毎日飲むのはそれと同じことである。私は甘いものを食べないしコーヒーも飲まないしテレビも見ないので、お酒を飲むことで1日を締めくくる。今日も頑張ったぜと思う(あまり頑張っていなかったとしても)。
そういえば最近、全く飲まなかった日があった。仕事が溜まり過ぎてどうにもならず、徹夜をした日だ。徹夜したのは、おそらく10年ぶりくらいである。
体力的に今さら徹夜できるだろうか、という不安はあったが、案外できるものである。翌日も朝から通常運転で仕事も家事もできたし、日中に眠くなることもなく、仕事は進んだし締め切りにも間に合った。夜には2日ぶりのビールを美味しくいただいた。
翌日にそれほど影響しなければ、徹夜は手持ちの時間を増やす有効な方法である。夜中から朝方まで6時間くらいの仕事時間を物理的に増やすことができる。これは隠れた資産である。いざという時のために取っておく貯金のようなもので、安易には使えないが追い込まれた時の最終手段になる。
私はこの時まで、自分は年齢的に徹夜できないと思っていた。しかし、それは思い込みであった。
同じような思い込みは他にもあるのではないか。何も変えられない人に共通する考えは、上を見る視点、横並びの意識、前例主義である。上を見る視点は、上司がダメというだろう、国がこうだからいけないと考えて最初から諦めるケース、横並び意識は、隣がこうだから、みんながこうだからと考えて現状に安住するケース、前例主義は、過去にやったことがない、うまくいかなかったと考えて挑戦を避けるケースである。
そんな自分になっていないか。知らず知らずにそんな思考になっていないか。
それを確かめつつ反省するのが毎日の晩酌の目的でもある(こじつけ)。
|
ゼロイチとイチヒャクについて 2月某日 晴れ |
ゼロイチ、イチヒャクという言葉がある。
ゼロイチは無(0)の状態から新しい商品、サービス、事業を作り出すことを指す。また、イチヒャクは生まれたばかり(1)の商品、サービス、事業を大きく育てていくことを指す。
ゼロイチは尖った発想や課題を発見する力が必要だ。一方のイチヒャクは人を巻き込んだりマネジメントしたりする力が求められる。この両方を兼ね備えている人は少ない。名プレーヤーが名監督にならないのもそれに通じるところがある。また、絶対数としてゼロイチができる人はイチヒャクができる人より少ない。日本に起業家が少なくサラリーマンが多いのもおそらくそのような偏りがあるからだろうと思う。
私はどうかというと、どちらの能力もそこそこである。物書きとして独立し、自営で食べているという点ではゼロイチであるが、物書きは大昔からある商売であり、つまりそこに事業としての新しさはないため、ゼロイチというよりはリスクを取れるかどうかの話だ。
国民性を数値で表すホフステッド指数によると、日本人は不確実性を回避する傾向が極めて高いという。数値で見ると、日本人の不確実性を回避する傾向は92ポイント、アメリカは46、中国は30である。たまたまだが私(独立した当時の私)は日本人らしい傾向がなかった。独立することへの警戒心が薄く、その延長線上に今がある。
イチヒャクに関しても、独立した時と比べれば収入は大幅に増えたが、人を雇ったり組織化して事業を大きくしたりしているわけではない。そもそも物書き商売がそういう展開に向いていないという事情もあるが、その点で私はリスク回避の考えが強く、人を雇う責任も負いたくないと思っている。
子を持つことや育てることもゼロイチとイチヒャクの考えに通じるものがあると思っている。人生という大きな視点で考えると、子を持つことは親になるということであり、親という新しい仕事を始めることである。これはゼロイチに通じる。また、子供を立派な人に育てていくことはイチヒャクである。ここで求められる能力を伸ばすことは仕事の能力を伸ばすことよりも楽しいしやりがいが大きい。社会的価値も大きいと思う。 |
確定申告について 2月某日 晴れ |
確定申告の時期である。
確定申告が不思議なのは、毎年やっているにも関わらず、毎年何からやるんだったか忘れることだろう。領収書を並べて、ソフトと国税庁のサイトを立ち上げるまではやってみるが、次に何をするんだったか迷う。
とりあえず領収書をコツコツと入力していくと、少しずつ記憶がよみがえってくる。そういえば、ここに入力するんだったなとか、ふるさと納税は寄附金控除だったとか思い出しつつ、どうにか2日くらいかけて申告が終わる。
去年は3月15日ギリギリの申告になった。ようやく出来上がったころ、国税庁のサーバーが落ちたのかなんなのか、申告書を送信できない時間がしばらく続き、焦った。
今年は同じ轍を踏まないように早めにやる。そう心に決めていたのだが、ずるずると時間が過ぎている。小学校の頃は夏休みの宿題をさっさと終わらせるタイプだったのだが、日々の仕事と家事でやることが多いという理由(言い訳ともいう)を掲げてギリギリで生きるカトゥーンみたいになった。
去年からの変化として、コロナ禍が少し落ち着きつつあるせいか旅費や接待交際費の経費が増えた。去年は取材で地方に行く機会が何度かあり、泊まりがけで大阪や福岡にも行った。これはコロナ禍になってからは初だ。ただ、その分、収入も増えたかというと増えていないのが不思議だ。ざっくりとしか計算していないが、去年(今年の申告)は収入が減っているはずである。収入が減るのは東日本大震災の時以来だから12年ぶりのことだ。
フリーで活動している知り合いなどからは、税理士さんに頼めばいいのにと言われる。確かにその方がラクだ。ただ、自分で申告する意味もあると思っている。
例えば、源泉徴収票や月々の売上を見ながら、誰からどんな仕事をもらったのかを振り返る。引き続き長く付き合っているお客さんもいるし、新たに仕事がスタートして、いい付き合いになっているお客さんもいる。一方には、単発の仕事で終わったお客さんもいる。そんな振り返りをしながら、感謝したり反省したりする機会は確定申告くらいしかない。その点で、フリーにとっての確定申告は個人にとっての大晦日のようなものだ。大晦日と違ってお酒抜きで振り返らないといけない点がネックではあるのだが。
ちなみに、確定申告について本稿を書いてはいるが、まだ終わっていない。むしろ、 |
自然について 2月某日 晴れ |
虫を食べるというおぞましい話の続き。
この件については、正直な感想として、驚くというよりゾワッとしている。私は虫が苦手だし、虫がいそうな自然豊かな環境も苦手だから、余計にそう感じるのかもしれない。
ところで、最近は都会暮らしに疲れて田舎に移住する人が増えているという。都会は常に忙しいし人が多すぎるから、それに耐えられない人は一定数いるのだろう。環境に馴染めないのは不幸だし、それがストレスになると精神的に病むことにもなりかねないから、そういう人は田舎に住むのがいいのかもしれない。
ただ、虫を食べる話の文脈で言うと、私は田舎で暮らしたいという気持ちも実はよく分からない。都市部は人が多いけれど、その分、お互いとの関係性が希薄だから気にならないし、気にしなくていい。日頃から付き合いがある人を除けば、街ですれ違う人が誰であろうと何をしてようと気にならないし、感覚的には街の風景の一部のようですらある。
田舎はそうはいかないだろう。自治体やら町内会やらの付き合いが心労になりそうだ。コミュニティが小さいほど知り合い度合いが増し、干渉し合う関係性ができるため、誰かにどこかで見られているような緊張感がある。
田舎暮らしに魅力を感じないそもそも理由は、海や山がそれほど好きではないからかもしれない。海で泳ぐならプールの方がいい。山で遊ぶならキャンプくらいで十分だ。私にとっての海や山は遊びに行く場所であって生活拠点にあるものではないということだ。
自然が好きだという人もいる。それが理由で田舎暮らしをする人もいる。
それはその人の好みだろうけれど、自然が好きなら子育てするか、近所の子供と接したらいいのに、とは思う。子供は自然そのものだ。人の個性は年齢や経験によって薄められるが、子供はそれがないから個性そのものでもある。わざわざ引っ越さなくても自然との接点ができる。
田舎や自然を下に見ているわけではない。自然は大事だ。田舎も大事である。
ただ、都市部で暮らしている人の特徴なのか、田舎や自然の価値は都会のおいて過大評価されているようにも思う。あるいは、田舎の人が都会に憧れ、都市部の人が田舎を目指すという関係を考えると、ないものねだりなのかもしれない。だとすれば、大事なのは老子がいうところの「足るを知る」こととも言える。 |
虫について 2月某日 晴れ |
私は虫が苦手だ。
嫌いというわけではない。昔から苦手なのだ。
幼い頃はカブトムシやらセミやらトンボやらを採ったこともあった。しかし、その頃もあまり触りたいとは思わなかった。周りがノコギリクワガタだのミヤマクワガタだの盛り上がっている様子もちょっと引いてみていたし、雑木林などに虫取りに行くと目当ての虫以外もいるし得体の知れない生き物もいるため、そういう場に行くことも苦手だった。
大人になると虫が苦手でも日常生活には支障がない。都会に住んでいると虫を見る機会もほとんどないし、蚊はいるが蚊取り線香をつけておけばいい。どういうわけか私は蚊に刺されないので、子供らがいなければおそらく蚊取り線香もつけなかっただろう。
そういう平穏かつ平和的な日常を過ごしてきた中で、これは問題だなと思う話が出てきた。コオロギを食べようと推奨する人や団体が現れたらしい。
これもSDGsの一環なのだろうか。たしかSDGsには「飢餓をゼロに」という目標がある。しかし、飢餓は重要な社会課題だとしても虫を食べなくてもいいだろう。そもそもコオロギは食べられるのだろうか。養殖してまで食糧にするらしいが、そこまでしなければならないほど世界は飢えているのか。
少なくとも日本は飢えていない。コンビニにもスーパーにも美味しい食べ物や食材がたくさんある。むしろ弁当や惣菜などは賞味期限切れで捨てられ、フードロスをどうにかしようという話が盛り上がっていた時期もあったほどだ。今もそういう議論はあるだろうと思う。
もちろんコオロギをそのままの姿で食べるわけではない。それは地獄絵図だ。しかし、だとしても原料としてコオロギを使っていると知って食べたいと思う人は少ないだろうし、いわゆるゲテモノ好きな奇特な人だと思う。
ラーメンを注文してコオロギが浮かんでいたら誰だって返品するだろう。ハエ1匹だったクレームになる。極度に虫が苦手な人なら失神するかもしれないし、まさか美味しそうなトッピングと思う人はいない。
感覚的なものだと言われればそれまでだ。しかし、食に関しては食べたいと思うかどうかが大事だ。私は食べたいとは思わないし、食べられる自信がない。 |
領土の拡大について 1月某日 |
いつまで続けるんだろうか。
ロシアがウクライナを侵攻したのは去年のこの時期だった。当初は、どうせすぐに終わるだろう、西側社会が許しておかないだろう、などと楽観的な見方もあった。しかし、気づけば1年が経つ。気にしてないわけではないが、気にしなくても日々の生活には支障がない私などは、すでに侵攻の大義すら忘れてしまった。プーチンも忘れているのではないか。それくらいこの侵攻は無意味であると思うし、無意味だからとっととやめたらいいのにと思う。
大義がなんであれ、侵攻の狙いは領土の拡大だと私は思っている。ロシアは狡猾な国だ。念のため断っておくとロシア人がどうこうではなく、ロシア政府の話。
第二次世界大戦の末期、ロシア(ソ連)は日ソ中立条約を覆して日本に宣戦布告した。日本に原爆が落とされたのを知った後のことで、終戦の数日前だ。
このタイミングで急に敵側につくのは普通の神経ではない。そもそも戦争が普通の神経ではないのだが、急に寝返り、そして領土不拡大の原則をも無視して北方領土を持っていくとは狡猾だなあと感心する。もちろん悪い意味で。
そうまでしてでも領土を南に広げたかったのだろう。ロシアはでかいが、その半分くらいは極寒で使いようがない。そう考えると、沖縄は返ってきたが、残念ながら北方領土が返ってくる可能性は非常に小さいように思う。ウクライナ信仰でしくじってロシアが解体するようなことがあれば話は別だけれども。
それはそうと、戦争が終わって80年近く経つわけだが、ロシアはいまだに領土拡大を狙っているらしい。その点ではウイグルなどの自治区や台湾への侵攻をやめない中国も同じだ(中国人がどうこうではなく、北京政府の話)。
今どきはネット社会であり、なんならメタバースの世界でもあるから仮想空間ではいくらでも領土が作れる。しかし、ロシアと中国は物理的な領土がほしいらしい。
冷戦が終わってベルリンの壁が壊れた。ソ連がなくなって東側社会と左寄りの政治は思想的に崩壊した。でも、実際には崩壊していない。時代が変わっていることを認識し、彼らの頭にこびりついている80年前の価値観が壊れない限り、戦争は続くし今後も起きる。つくづく無意味だなあと思う。 |
道徳について 1月某日 晴れ |
自業自得だなという気もするし、ネットは怖いなあとも思う。
開店寿司チェーンで悪事を働く人たちの動画がSNSで拡散されている。カラオケ店で暴れたり、バイト先でイタズラしたりする人の動画もあっという間に拡散される。
私は性格的にも思考的には決して品行方正ではないので、中高生の時代にスマホがあったとしたら調子に乗って似たようなことをやって人生が終わっていたかもしれない。そう思うと恐怖はなおさらである。時代に追いつかれなくてよかった。
そういう素養が自分の中にあったとしても、なんだかんだ品行方正に生きているのは、それが人として、大人として当たり前だということはもちろんだが、ルールは守るものという意識が頭のどこかにあるからだろう。
私は、ルールと約束と子供は守ると決めている。いつからそう考えるようになったのか。子供については子供が生まれてからだが、ルールと約束に関してはもう少し前から守っているように思う。おかげでルールという点では交通違反などはないし、約束に関しても集合時間に遅れたことはない。原稿の締切についてはたまに遅れるが、自分なりの言い訳として、勝手に遅れるのではなく相手の許可を得てから遅れているので、その点では約束を守らなかったことにはならないと思っている。
言い換えると、守っているのはこの3つくらいで、あとはどうでもいいと思っている。例えば、世の中にはプライドやメンツを守ろうとする人がいるが、私はそれらはどうでもいい。プライドを持てるような人生ではなかったことや、肩書きが裏打ちするメンツなどがないというのも理由だろう。
それはそうと、日本はこれから人口が減っていく。日本には資源もない。その中で国力を維持し、成長させていくためには、子供を増やす(減らさないようにする)か教育レベルを高めるか道徳心を磨くしかないと思っている。実際、それで日本は世界2位の経済大国にまでなった。
今の日本が衰退途上国に成り下がっているのは、この3つが欠けているからではないか。例えば、SNSで子供たちが炎上する原因は教育と道徳が足りないからだと読むことができる。要するに、幼いときの教育と家庭教育に日本再興の引き金があるような気がするのである。 |
自分について 1月某日 晴れ |
エゴサーチという言葉がある。
生まれて初めて、ふとエゴサーチしたい気持ちが盛り上がった。ChatGPTの存在を知ったからである。
ネットという無限の宇宙から私に関する情報を集めると果たしてどうなるのか。そんなことを考えて、ChatGPTさんに自分のプロフィールを書いてほしいとお願いした結果が以下(コピペ)である。
「伊達直太(だてなおた)は、日本の小説家・ライターであり、1982年生まれの現役医師でもあります。大学在学中から小説を執筆し、2009年にはデビュー作『掌の小説集』が刊行されました。その後、多数の小説やエッセイを手掛け、2013年には『人間失格』の現代版として話題となった小説『おとなになるということは』を刊行しました。
また、医師としての知識を生かし、健康や医療に関するエッセイやコラムも執筆しており、多くの読者から支持を受けています。近年では、メンタルヘルスに関する著作も手掛けており、『マインドフルネス入門』や『ストレスフリーに生きるための12の習慣』などがあります」
細かく見ると笑っちゃうくらい間違っているのだけれど、重要なのは、一部でも合っているということだ。世の中には70億人くらいいて、そのなかの無名な1人を少しでも特定できるのは、ちょっと恐ろしくもある。
賢い学者先生によれば、AIが人間の能力を超えるシンギュラリティは2045年であるらしい。その頃には、例えば、どこに住み、どんな仕事をして、どんなビールを好むのかなど、個人のあらゆる情報を誰でもどこからでも把握できるようになるのかもしれない。ちなみに私は一番搾りが好きである。こういう情報を進化し続けるAIが拾って、誰かが一番搾りを贈ってくれたりしないだろうか。
ところで、私が書いた(ことになっている)『おとなになるということは』は、ちょっと読んでみたい気がする。もちろん、そんな著書は存在しないが、AIの世界では「話題になる」ことが分かっている。ならば、書けばいいじゃないかとも思う。それはつまりAIの示唆によって人の行動が作られるということであり、AIによる人間の支配は実はすでに始まっているような気もする。 |
今年の課題について 1月某日 晴れ |
新年明けましておめでとうございます。
2023年もよろしくお願いいたします。
おかげさまでバブルが継続中である。
気づいたら年が明けていた。毎年、年末は仕事が重なることが多いのだが、この年末年始は過去最高に重なるミルフィーユであった。
私はリアルタイムでは知らないが「24時間戦えますか」というフレーズが流行語になったバブル経済期のように、24時間体制で原稿を書いている。実際、先日は10年ぶりくらいに徹夜で仕事をした。まさかこの歳になって徹夜することになるとは想像もしていなかったよね。
もちろんバブるのは良いことだ。徹夜覚悟で新人のつもりで頑張ります。そんな気持ちで今年も仕事と向き合いたいし、そういう謙虚な気持ちでスタートする年始は悪くないと思っている。
そんなふうに思う一方で、そろそろ今の事業モデル(というほどものではないけれど)が限界なのかなとも思う。そもそも人(個人)が提供できる資源は限られていて、体、頭、心、時間、お金の5つくらいしかない。体は肉体労働、頭は知的労働、心は接客、時間はアルバイト、お金は投資や運用である。
商売とはつまり、これらを使って人の役に立つことであり、その対価としてお金が入ってくる。物書き商売の事業モデルは、頭、心、時間の3つをお金に変えることだ。時間に追われるということは、この3つのうちの時間というリソースが限界に達しているということである。
私はもともと時間主義なのであらゆる角度からタイムパフォーマンスを高めようとしてきたのだが、この半年はずっと時間(締め切り)に追われた。それも今の事業モデルが限界に近づいていることを示す要因の1つだと思う。
この状態から脱却する方法はいくつかある。例えば、投資はその1つで、投資は、体、頭、心、時間、お金の5要素のうち、頭とお金でお金を生むモデルであるから時間は減らない。そう思って投資を始め、そろそろ歴も10年になるわけだが、これがなかなか儲からない(むしろ損している)から難しい。
さて限界が近づいている感じがする中で物書き障害の事業モデルをどう変えたらいいのか。これを本年の課題にしたいと思う。
そんなわけで2023年もよろしくお願いします。 |